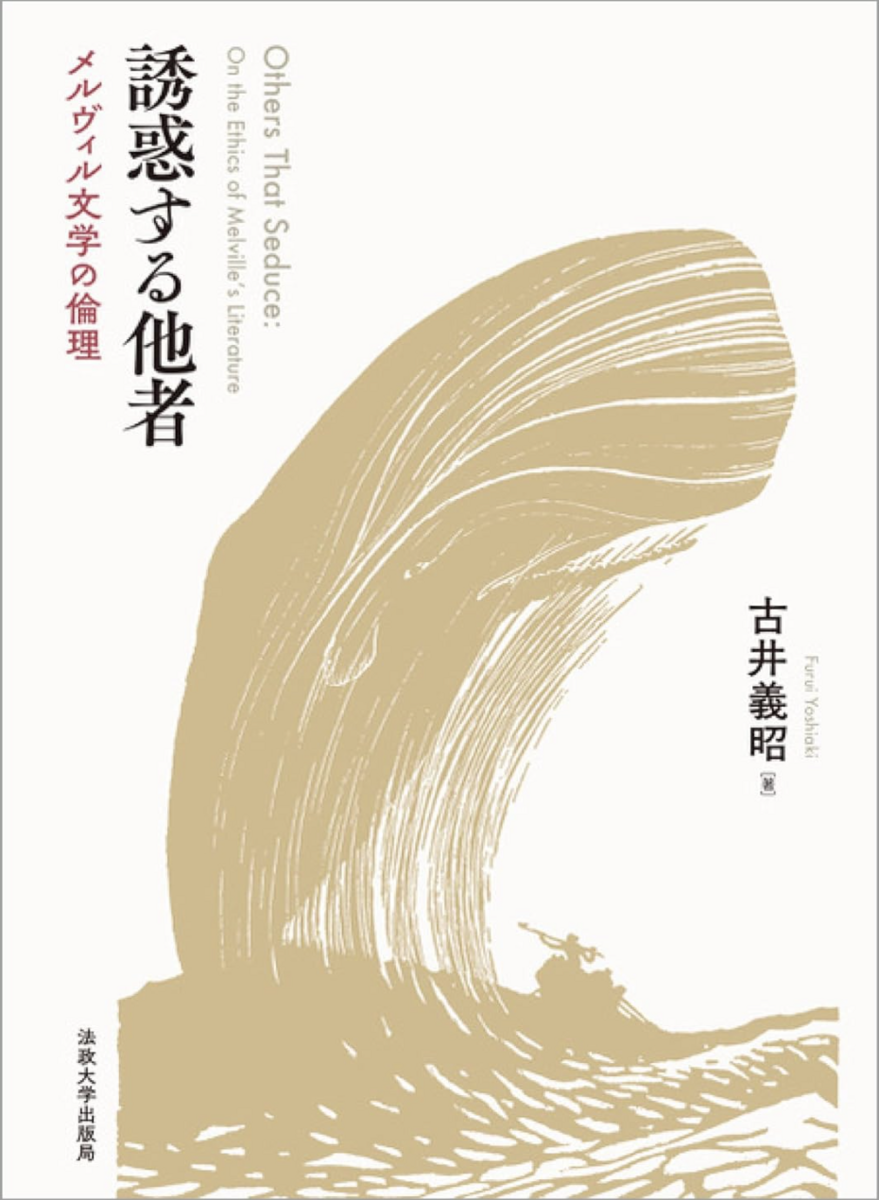古井義昭『誘惑する他者:メルヴィル文学の倫理』の取扱説明書
古井義昭『誘惑する他者:メルヴィル文学の倫理』が法政大学出版局から刊行された。本エントリは、本書のおそらく最速にして、今後だれも書かないであろうタイプの、奇怪な1万字の書評である。
Amazon.co.jp 古井義昭『誘惑する他者:メルヴィル文学の倫理』
いそいで最初に言っておかなければならない——本書はハーマン・メルヴィルという19世紀のアメリカの小説家についての専門書なのだが、以下の文章は、メルヴィルにも、アメリカにも、文学研究にも関心がない読者にむけて書かれている。念頭にあるのは人文系の院生や研究者だが、もしかすると一般読者にも楽しんでもらえるかもしれない。
そもそもわたしはメルヴィルという作家について、おそらくそのへんの海外文学好きの読書家たちよりも無知である。以下は、人文系の論文の書き方を学ぶための参考書として本書を活用するための取扱説明書だ。
本稿が注目するのは、本書の内容よりも、形式である。すぐれた論文から論文の書き方を学ぶにあたっては、ヘタに内容について詳しい論文は使わないほうがよい。なぜなら内容に気を取られてしまい、形式への注意が疎かになるからだ。むしろ内容に専門的な興味がない論文こそ、形式の抽出にはむいている。
もしあなたが、わたしをアカデミック・ライティングの教科書の執筆者として認知している読者なら、本書『誘惑する他者』は間違いなく現時点で手に入れられる最高の和書なので、あなたがどんな分野にコミットしていようとも、間違いなく役立つことを保証する。これよりも優れた和書が出ることは、すくなくとも今後10年はないだろう。
わたしは何人もの優れた書き手をモデルとしてアカデミック・ライティングの方法論を構築してきたが、そのなかでも古井は、トップスリーに入る先達である。以下でとりあげる論文は、どれも一時期わたしが印刷してつねに持ち歩き、ボロボロになるまで解析したものだ。
わたしも多産な古井に劣らぬペースで、古井に劣らぬ論文を書いてはきた。だが執筆の方法論を学ぶためには、わたしのガチャガチャした素行の悪い論文たちよりも、古井の端正で、堅実で、模範的な論文のほうが向いている。じっさいわたしは論文指導にさいして、つねに自分の論文ではなく古井の論文を読むよう薦めてきたし、今後もそうするつもりだ。
古井の本は、全10章のうちほとんどすべてが海外誌から出版された査読論文である。このような和書は、おそらく同分野において、それに近い前例すらないだろう。この意味でも古井のメルヴィル論群が日本語訳されたことには、きわめて大きな教育的意義がある。本稿では、とくに国内の全国誌レベルから海外誌へとステップアップする段階にフォーカスして解説したいと思っている。
わたしはすでに、査読論本をまったく出していないか、あるいは1本だけ書いたのちに停滞しているような初学者にむけて、本ブログで勉強法を紹介した(「アートとしての論文」)。各読者のレベルにあわせて、本エントリをこれと併せて読んでもらえるとよいと思う。上エントリでは「多産な若手の論文を縦断的に読むとよい」と書いているが、以下はその実践例のひとつである。
ちなみに古井はわたしの東大の大学院の先輩にあたるが、彼と一緒に教室で学んだことは一度もなく、むろん教わったこともない。勝手に私淑し、その論文を自分の執筆技法の構築のために使わせてもらってきただけである。
◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎
『誘惑する他者』は、古井が2010年から2022年まで、じつに12年間にわたってメルヴィルについて書き綴ってきた査読論文を集めたものである。チャプターの配列は出版年度順ではなく、テーマごとに区切って並べ替えている。
われわれの目的はここから書き方を学ぶことであるわけだが、わたしはよく論文執筆の指導で、ベテランの研究者が書いた最近の論文は参考にしないよう教えている。わりあいキャリアの初期に書かれたぎこちない論文のほうが、論文のルールをリジッドに守っており、アクロバティックな要素が少なく、参考にしやすいのだ。
というわけで論文と掲載媒体を出版順に並べ替えると、以下のようになる。
『ピエール』論、『アメリカ文学研究』英文号
『信用詐欺師』論、Leviathan
『ベニト・セレノ』論、Canadian Review of American Studies
『ジョン・マー』論、Leviathan
「バートルビー」論、Journal of American Studies
『白鯨』論、Criticism
「エンカンタダス」論、Leviathan
「ビリー・バッド」論、Literary Imagination
『イズラエル・ポッター』論、Texas Studies in Literature and Language
ここから論文の書き方を抽出するにあたって、太字にした3本を使いたい。いちばん最初の『ピエール』論、2本目の『信用詐欺師』論、そして「バートルビー」論である。最初の2本は古井のresearchmapで公開されていて、英語の原文も読むことができる。
すこし説明しよう。古井の論文は、およそ3種類に分けられる。第一に国内誌の論文。第二に、海外の中堅誌か、その少し下の媒体に載せた論文。そして第三に、トップ層のジャーナルである Journal of Amerncan Studies の掲載論文である。
(1)最初と最後が日本国内の媒体になっているが、『ピエール』論と『タイピー』論には12年のひらきがあり、前者は「あとがき」に説明があるように古井の修士論文、後者は、のちに10本以上の論文を書いて博論も書籍化したあとの古井の論文であり、これらはまったくクオリティが異なっている。初学者が参考にすべきは、完成度の高い後者ではなく、前者である。
(2)国内誌論文と「バートルビー」論を除いた7本は、ほとんど中堅誌か、その少し下の、いわゆる 3rd tier journal に掲載されている。古井は修論から国内誌に『ピエール』論を載せたあと、留学してわりと早い段階でメルヴィルの専門誌である Leviathan 誌に『信用詐欺師』論を掲載している(タイミング的にこれは期末レポートだ)。本エントリでは、ここでの国内誌から海外誌への飛躍を捉えたいと思っている。
(3)「バートルビー」論が掲載された JAS という媒体はアメリカ研究では世界で2番手のジャーナルで(トップは American Quarterly)、本書のなかで浮いている(ただしこれはイギリスの媒体で、米国とは評価基準が異なる)。中堅誌に大量に書いている古井の論文群のなかで本論を読むと、その少し上を目指すためのヒントが詰まっていることが浮き彫りになる。じっさいわたしは本論が古井のベスト論文だと思っており、その理由も、あとで述べる。
ざっとこんな感じである。順に読んでゆこう。
◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎
論文からフォーマットを抽出するさい、もっとも注意して読むべきはイントロダクションである。とくに重要なのは、段落数と、各段落の機能だ。
古井論文のイントロダクションはおおむね2から4段落からなっている。例外は比較的あたらしい『白鯨』論と「ビリー・バッド」論で、前者はじつに8段落もある。メルヴィルといえば『白鯨』であり、本書の第1章も『白鯨』論になっているので、ここで書いておくが、『白鯨』論は本書のなかでもっとも論文のフォーマット抽出には使いにくい論文である。以下を読んでから『白鯨』論のイントロを読めば、それがいかに初学者には真似しにくい論文であるかわかるだろう(それもぜひやってみてほしい)。
さて、古井はだいたい2から4パラでイントロを構築している。イントロダクションにはその論文がどういう論文なのかをすべて書かなくてはならないので、イントロを読めば、その論文の規模をほぼ正確に判断することができる(じっさいわたしは査読の現場ではイントロを全部読まないうちにリジェクトすることが多々ある)。
さて、『ピエール』論のイントロは3パラである。それぞれのパラグラフの内容を要約してみよう。
1)『ピエール』の主題として、「血縁」と「書くこと」が挙げられる。
2)「血縁」と「書くこと」は先行研究で別々に論じられてきたが、併せて論じる必要がある。そのために「手紙」というテーマを導入したい。
3)「ピエールは小説を書くことで独立した自己を獲得できるのか」を問い、ピエールが他者としての自己に向き合うことを拒否するキャラクターであることを示す。
各パラグラフの機能を言語化してみよう。
1パラは『ピエール』から「血縁」と「書くこと」というテーマを抽出している。このように、ある対象におけるモチーフに着目するというのは文化研究では初歩中の初歩であり、初学者がまず第一に書けるようになるべきは、こうした「A(対象)におけるB(着眼点)について」という形態の論文だ。学部生も指導なしでここまではできるが、古井はそれを2つ挙げている。
2パラは重要である。ここは元の英語論文とけっこう違っているのだが、先行研究にごく短く言及することで、先行研究が不十分であると批判し(血縁書くことは併せて論じられてこなかった)、なおかつこの論文のアカデミックな価値がどこにあるのか明言している(併せて論じる)ことを理解してほしい。「先行研究はAに着目してこなかった」という批判は、初学者にもすぐに実践可能な、もっとも単純なタイプの、アカデミックな価値のつくりかたである。とくに学振DCでは、ほとんど100%の学生がこのタイプの説明で書類を書いてくる。
3パラでは「自己」という新しいトピックが導入されるが、1、2パラとの接続が不明瞭である。もし修士課程の古井をわたしが指導するのなら、血縁と手紙のモチーフがいかに自己や他者といったテーマと接続されるのかを(できれば自己の問題だからこそ血縁と手紙はあわせて論じられなくてはならないのだという方向で)イントロで言語化するように伝えるだろう。このパラグラフは、2パラで出てきた本論のアカデミックな価値(先行研究の批判)とは関係がなく、ようは「自己の話もします」と言えているにすぎない。また、じつはここに「ピエールは他者としての自己に向き合うことを拒否する」という本論におけるもっとも重要な主張内容が含まれており、書き手はここを読者に引用させなくてはならないのだが、このイントロは、どんな読者にもこの箇所をハイライトさせられるように書けていない。たぶんあなたがこの論文を引用するなら、血縁か手紙について書いてしまうだろう。だがそれはテーマであって主張ではない。
というわけで、本論のイントロがやっていることは、①作品を選び、②そこに現れるテーマを抽出し、③先行研究の批判によって論の価値をつくる、ということまでである。きわめてベーシックで、真似しやすい、初学者にとってのお手本のような論だ。以下でより高級な論文の書き方に触れるが、1、2本目の査読論文は、このくらいのミニマムな規模で書くべきである。
ここからテクニックとして学べることは、「あるテーマを抽出して、先行研究が不十分だと言う」まではほとんどの修士学生が指導なしでもやろうとすることなのだが、古井の場合は2つのモチーフを抽出して、それらは「併せて論じないとダメなのだ」という論法で批判を展開していることだ。これは誰にでもすぐに真似できる手法であるように思われるし、論じたいテーマが複数ある場合にひろく応用できる技術であるだろう。
もし興味があるひとは、このあとのパラグラフもこの調子で解析してみるとよい。各パラグラフの機能をこのように分析する、わたしが「パラグラフ解析」と読んでいるこの勉強法は、論文執筆のトレーニングとしてわたしの知るかぎり一番効果が高いものである。
◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎
つづいて『ピエール』論と比較するかたちで、古井の2本目の論文である『信用詐欺師』論のイントロを解析してみよう。これもやはり3パラからなっている。
1)『信用詐欺師』の主題として障害を挙げたうえで、障害学(disability studies)を用いた近年のメルヴィル研究に言及。
2)19世紀半ばのアメリカにおける身体障害という歴史的背景に『信用詐欺師』を位置付け、前段落で言及したメルヴィル研究の内容を簡単に紹介。
3)さらに個別の研究に踏み込み、本論はそのどれとも異なる点(障害者の内面)に着目する点が新しいと述べることで、本論のアカデミックな価値がどこにあるのか明言。
ふたたび詳しく言語化してみよう。
1パラは、『ピエール』論と同じく、まずは作品+テーマを設定している(『信用詐欺師』と障害)。これが『ピエール』論よりもすこしだけレベルが高いのは、それがたんなるモチーフの指摘(血縁と手紙)ではなく、障害学というアカデミックな言説の枠組みでそれを捉えるという点まで言えていることだ。『ピエール』から血縁と手紙というモチーフを抽出することは素人でもできるが、『信用詐欺師』の障害というモチーフを障害学の枠組みで読むことは専門的な知識がないとできない操作である。このレベルで論が成功すれば、もはや日本の学会誌ではトップクラスだ。
2パラは、1パラで導入した障害学という超時代的なテーマを、作品が書かれた当時の歴史的背景に位置付けることで、本論が理論論文ではなく歴史論文であることを宣言している。さらにサミュエルズという、おそらく同トピックの最重要先行研究を直接引用しているが、この引用で明らかになるのは、公共空間と障害(者)という本論が扱おうとしているトピックが「重要である」という点までである。つまりこの時点では、「いろいろなひとが重要だと言っているこのトピックについて本論も語ります」と言えているにすぎない。
3パラは、かなり長いうえにゴテゴテしており、邪推するに、はじめて海外誌の査読者からの厳しいコメントに触れ、それに応えようと院生の古井が頑張った結果なのではないか。まぁそれはいいとして、ここではシュワイクという(おそらくメルヴィル論者ではなく)障害学についての議論でのよく知られた枠組み(超可視性と不可視性)、ならびに先行するメルヴィル論における「障害者の内面と外見」という議論を引いて、本論はそのいずれからも距離を取る、としている。
『ピエール』論との違いは、ここですでに先行研究を具体的に何本も引用し、それらとの差異をイントロで示し終えていることだ。『ピエール』論では血縁と手紙というテーマが併せて論じられてこなかったことを批判していたが、ここでは先行研究が依拠あるいは提出する具体的な枠組みをダイレクトに批判している。そのうえで、「障害者の身体という外的指標ではなく、障害者と見なされる者の隠された内面」が重要なのだという主張を展開できている。
これがなぜ論文として『ピエール』論よりもアカデミックな価値が大きいのか考えてみよう。これは、メルヴィルなどに興味がない読者にこそ、むしろ理解しやすいものである。
『ピエール』論のイントロから、あなたはなにを学んだだろうか。ちょっと考えてみてほしい。おそらく、メルヴィルの『ピエール』という一生読まないであろう作品において血縁と手紙というテーマが現れ、それらが密接に結びついている、ということぐらいであろう。メルヴィルあるいは古井に興味があるか、あるいはまかり間違って『ピエール』を読むことがないかぎり、あなたにはこの論文を最後まで読むモチベーションはないし、そこから持ち帰るアイディアも、ほとんどない。
それに対して『信用詐欺師』論のイントロでは、障害学や19世紀のアメリカにおける障害者の現れ方とそれについての法律なども学べるのだが、重要なのはそこではなく、古井の論が、「障害者が公共空間でどう見られたかではなく、障害者自身の内面を見なくてはならない」という観点を提示していることだ。この発想は、『信用詐欺師』を一生読まないあなたやわたしも、どこか別の機会で障害一般あるいはフィクションにおける障害表象について考えるときに、応用できる可能性がある。
つまり大局的にみたとき、学問的な価値とは、たとえば文学研究なら作品をどのくらいエレガントに面白く読むかなどというところにはなく、あくまでもポテンシャルとして、その論文をどのくらいの人が読みえ、どのくらいの人がみずからの議論に応用しうるかにある。それはつまり、参照可能性の問題だ。
ここに海外誌から出すために必要不可欠なポイントがある。論述が精緻であるなどということは海外誌においては大前提であり、ジャーナルがその論文を出版したいと思うかどうかは、引用されるかどうかにかかっている。教育機関である日本の学会誌では査読者が投稿者の論のクオリティを判断するという上下関係があり、それゆえに論のクオリティさえよければ採用してもらえるのだが(これはこれで存在意義がある)、研究の場である海外誌では筆者と査読者は対等であり、こちらも相手と同等のプロフェッショナルであることが求められる。そして彼らがプロの研究者に当然のごとく要求するのは、アカデミックな世界への知的貢献であり、それは、被引用可能性でしか測定されることがない。
別の言い方をすれば、古井の論文はわれわれに『信用詐欺師』をどう読むかだけでなく、障害について、そして障害という着眼点でなんらかの対象を分析するということについて、なにかを教えてくれる論文なのである。まだまだ本論においてはその方法論は未熟だが、古井の論文をこの視点で時系列順に追ってゆくと、そこの技術がどんどん洗練されてゆくさまを目撃することができる。本エントリで分析しない論文についても、各自で見てもらえるとよい。
◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎
この点でもっとも優れているのが「バートルビー」論だ。このイントロは4パラからなっている。
1)ほとんど何も喋らないバートルビーというキャラクターの内面(なに考えてるか)を読者は知りたいと感じる、という導入。
2)この「他者の内面を覗きたい」という欲望には暴力的な側面があるとしたうえで、情動理論(affect theory)という学問的な言説に位置づける。
3)文学研究の領域においてさかんに論じられ発展してきた情動理論の歴史を整理し、 emotion とは異なる「言語化できない領域」として affect が論じられてきたのであれば、それを言語芸術である文学に応用することなどそもそも可能なのかと問う。
4)「バートルビー」において、この他者の内面(情動)は、描写されるのではなく暗示されるにとどめられている、として、そこに書き手であるメルヴィルの倫理があるのだと結論する。
1パラはやはり「バートルビー」と内面、すなわち作品+テーマという導入である。
2パラは、『信用詐欺師』論を読んだあとだと簡単にわかるように、素人読者でも抽出しうるテーマ(血縁、手紙、障害、感情)を、近年のアカデミックな言説である情動理論へと接続している。ちなみに『信用詐欺師』論ではここまで1パラで終わっていたので、3から4にパラグラフが増えたことに本質的な意味はないことがわかる。
3パラが重要である。ここでは、アフェクト理論という大規模な言説体系に対して、そもそも文学研究でアフェクト理論って矛盾してないか?という根本的な批判を提出している。これは歴史論文ではなく理論論文であり、この論文が提出しうる理論的介入の潜在的な最大値は、そもそも文学研究にアフェクト理論は適用不可能であるという指摘である。ここでは個別のメルヴィル論を批判しているわけではなく、文学研究におけるアフェクト理論の応用をすべてひっくり返すポテンシャルを秘めており、その規模において、他の論文とは完全に一線を画している。
しかしそんな批判が可能なのか。しかも「バートルビー」を情動理論で読もうとする本論で?4パラでは、「バートルビー」は内面を知りたいという欲望をかきたてはするものの、その欲望の暴力性に自覚的な作品であり、バートルビーの内面を完全に言語化するようなことはしない、そしてそこにメルヴィルという作家の倫理があるのだと結論している。本論の結論はアフェクト理論についてではなく、メルヴィルについての結論である。3パラで垣間見える貢献度が「潜在的な最大値」であると書いたのは、そういうことだ。というわけで、本論がタイトル「誘惑する他者」と「メルヴィル文学の倫理」をもっともダイレクトに反映する、実質的なタイトル・トラックだといえる。
『信用詐欺師』イントロの解説を読んだあとであれば、このイントロがいかに巨大な被引用可能性を持っているかわかるはずだ。affect とは感情のうち言語化できない領域を指すはずなのに、それを言語芸術を分析対象とする学問たる文学研究に無批判に応用してしまってよいのだろうかという批判は、およそ感情というものを描かない物語がおそらくこの世に存在しない以上、きわめて広範な応用可能性を秘めている。それは「バートルビー」の読者やメルヴィリアンどころか、文学研究者やアフェクト理論の専門家、そしてあらゆる物語の鑑賞者が参照しうる着眼点であり、さらなる思考を刺激する。
これを聞いただけで、たぶんあなたも、なんらかの作品なり経験なりを思い浮かべ、あるいはフィクション作品と感情という問題について何かしら考える刺激を受けることだろう。それがつまり、応用可能性、そして被引用可能性ということであり、つまるところ、いい論文だということなのである。
◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎
というわけで以上、パラグラフ解析の実践と、論文評価の着眼点をデモンストレートした。こうした視点で古井の他の論文、まったく別の著者の論文、さらには自分で書いた過去の論文などを読んで評価してみてほしい。論文というものの見え方がどんどん変わっていくはずだ。
さいごに古井の「バートルビー」論を批判してみよう。これをもっとデカい論文に鍛えるには、どんな可能性が考えられるのだろうか。
古井論文の構造は、アフェクト理論の根本的な矛盾を指摘したうえで、「しかしメルヴィルはこのように倫理的だったので偉いです」という結論に着地するというものだ。論の後半では、「バートルビー」以外のメルヴィル作品にも同様の倫理が見られるというふうに展開している。つまりここでアフェクト理論についてのメタクリティカルな思考は、最終的にメルヴィル読解に奉仕している。すなわち、これはメルヴィル論文であって、アフェクト理論論文にはなっていない。当然だが、メルヴィルについて新しいことを言うよりも、アフェクトについて新しいことを言えたほうが論文の価値は大きい。
「バートルビー」論のポテンシャルは、アフェクト理論の文学研究への応用可能性の再考にあった。そのポテンシャルを最大限に引き出すには、むしろメルヴィルをひとつの事例へと押し下げ、小説と感情の問題を中心に論をまわすことができればよい。
どうすればよいか。ヒントとなりそうな一案を出しておこう。
たとえば、作品分析パートで、3人の別の作家を扱うとどうなるか想定してみよう。そこでは、作家Aはこう、作家Bはこう、作家Cはこうでした、というそれぞれの小結論が導出される。そうなると、「ABCはそれぞれこうでした」は論文の結論になりえない(古井の論文はそうなっていた)。それら3つの文学におけるアフェクトが、最初の根本的な批判との関係においてどのような意味を持つのかに論を回帰させなくては、結論を導けなくなる。つまりこうすると、着地点がアフェクト理論についての言明にならざるをえない。
そこでどのような具体的な事例を用いて、どのような結論、つまり主張を導けばよいのか、わたしは知らない。それはトップジャーナル論文規模の結論であり、アフェクト理論を広く学ばなくては思いつくことさえできないからだ。
だがアフェクト理論についても、メルヴィルについても、ほとんど何も知らなくても、古井の論文をここまで読み、評価することは、練習すれば誰にでもできる。人文学における研究者としての実力とは、メルヴィルやアメリカや文学にどれだけ詳いかなどではなく、このように学術論文が読めること、そして、書けることなのである。
◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎ ◻︎
追記:本書の発売日は3/11だが、このエントリを公開した3/9時点ですでにAmazonでは「予約注文」と書いてあるものの「在庫あり」になっており、すでに買えば発送される模様。